あなたは、ご自身のキャリアについて考えたことがありますか?
Contents
ニンジンを追いかけてはいけない
教師は目の前の生徒に対して、寸暇を惜しんで貢献しようとします。ですが、自身のキャリアについて深く考えている教師は、ほとんどいません。
教師の仕事が楽になることはありません。価値観の多様化が進む中で、未来社会に生きる次世代を育成しなければならないからです。
次世代育成は価値ある行為ですが、それは同時に、「目の前にぶら下がったニンジン」でもあります。
生徒の成長に寄与している充足感に酔い続け、ふと気がついたら、自身の目標を達成できないばかりか、私生活の多くを犠牲にしたまま定年を迎えてしまった。
そんな人生を送ることになりかねません。
もしあなたが、ご自身のキャリアについて考える機会を持たないまま現在に至るのであれば、あなたの気持ちを確かめる方法があります。
誰も「センセイのキャリア」について考えてこなかった
『学校のセンセイのためのキャリア構築ガイドブック完全版』
当協会が作成した、15万字にわたる書籍です。
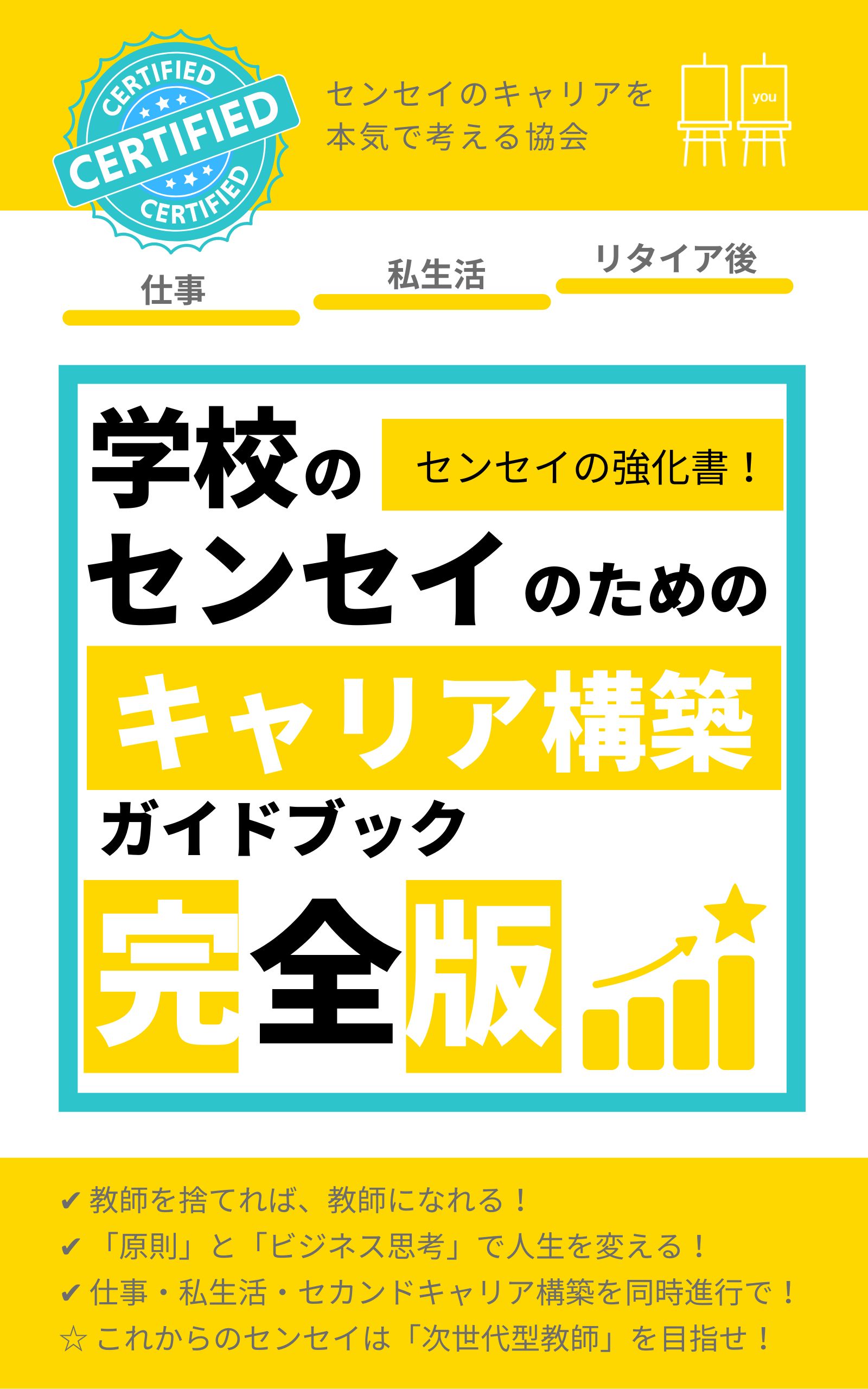
2023年3月末をもって、公立高校の教員歴30年を迎える教師が、次世代を担う教師像について記しています。
本書の特徴をただひとつだけ挙げるとすれば、「人生すべてを網羅した視点から、一個人としての教師が幸せになるための考え方や方法について述べている点」にあります。
今まで、そんなことを言った人は誰もいませんでした。
✔ 教師は自分のことを二の次にして教育に邁進すべし
✔ 教師はすべての教育ニーズに応えるべし
✔ 教師は校務に精通すべし
・・・こんなことばかりです。でも、そうすることで誰も幸せにはならなかったように思います。
学校の先生が幸せにならなければ、先生と長い時間をともにする生徒たちも幸せにはならない。先生の家族や身近な人たちも、きっと幸せにはならない。
教師は、自身のキャリアについて長期的なビジョンを持ちながら仕事に取り組むことで、最大限の力を発揮します。だから考えてほしいんです。自分がどんな人生を送りたいと願っているのかを。
レビューを紹介します
【読んでみようと思った動機】
私は40歳で教員生活を始めました。
初任としての初日。管理職から「半年見ていて、駄目なら不可を出す。そのつもりで。」と言われた時、公務員の安定性を考えていた自分の甘さに気が付きました。
「教員生活は、20年あるかないか。」「その20年の中で、セカンドキャリアとして何ができるか。仕事と私生活を並行させながら実行していかなければ、自分の人生を納得できるものにすることができない。誰かの幸せのために貢献することすらままならない。」と考え始めました。その時に、協会代表の方の投稿に出会いました。『教師であることを捨てる』
『私生活で成功する』
『学校の外で通用する力を持つ』上記の言葉が心に残っています。もやもやしていた気持ちがそこに言語化されていました。本書を通して自分自身の心を見つめ直したい。そう思ったことから読んでみようと思いました。
【共感できた点とその理由】
以下の文章に共感しています。
『人生を構成する要素は3つ』
『1 仕事』
『2 私生活』
『3 未来への可能性』生きていく上で、仕事は大切です。でも自分が「教育マシーン」になっても、誰も幸せにすることができないと考えます。
上記要素の3つは、バランスを取ってこそ人生を幸せにすることができると考えます。臨時的任用教員、初任、2年目の頃は、教員として力量を高めたい。指導力を身に付けたい。と、私生活を犠牲にしてまで教材研究をしたり、セミナーで学んだりしていました。
でも、私生活を犠牲にすることで、家族とのぎくしゃくした関係、心の疲れが蓄積し、体調不良が続き、常に不安感をもつ不自然さを感じるようになりました。本書を拝読してから、
『勤務時間内で集中する仕事の在り方』
『自分の時間をもつ私生活の充実』
『セカンドキャリアについて構想を練る』を実践し始めました。
以下、具体的な変化です。
1 『個別指導の導入や休み時間に、楽しそうに子供たちと対話をする』
2 『家族との対話が増え、いつも応援してくれることへ感謝の気持ちとやる気が増えた』
3 『セカンドキャリア構築に向け、具体的に行動するようになった』本書を通して、教員の仕事の一つは、「子供たちに一人の大人として幸せな人生を送っている様子を背中で示す」ことかなと感じます。
「社会人としてこうあるべきです。」なんて、子供たちに言えるほど、引き出しは持ち合わせておりません。
それよりも、「人としてどうありたいか。」「人を喜ばせるために何ができるか。」「得意を伸ばす、活かす活動に取り組む楽しさ。」を体現している姿を見せることが子供たちに「あんな大人になりたい」「大きくなったら○○をやってみたい」など、「未来への希望」を心に育てることができるのではないかと考えます。【どんな人に本書をお薦めしたいか】
「教員生活をただ時間の流れるままに過ごしていいのだろうか。」
「教員生活だけで、人生の幸せは満たされないのでは。」
「仕事・私生活・未来への展望についてバランスを取って行きたい。」
「学校の外と関係をもち、どんな価値を提供できるか模索したい。」一度だけの人生。その充実のために、変化に対応できる素地を身に付けたい。そのような方にお薦めしたいです。
身近な人から本書を薦めていくことで、セカンドキャリア構築について真剣に考える教員が増えていくことを願っています。
東京都 40代女性 小学校教諭
読みやすい文体で、「次世代型教師を一緒に目指そう」という著者の方の志がひしひしと伝わって来ました。
年長の教師が教師に対して書くと、ともすると、読み方によっては「こんなこともできないのか。」と責められているように感じる文章になることもある中、著者の方の文章はお人柄がうかがえる温かさが感じられました。これなら私も同感できるし、仲間に入れてもらいたい!と思いました。
章ごとに具体的に目指す姿が箇条書きで記されていて分かりやすく、自分の頭の中でも整理がしやすかったです。この文章を読んで、仲間として、新しい時代を生きる教師像を持つ人が増えるといいなと思いました。
自分の心の安定をもつために、著者の方が行っておられることなどがあれば、さらに読んでみたいと思いました。
読ませていただき、よい機会を得ることができました。
神奈川県 50代女性 小学校教諭
ありがとうございましたm(__)m。
今の教育現場で大きな課題となっている「働き方改革」「教員志願者数の低下」。
枝葉の対策は色々出されていますが、それらはお茶を濁す程度。
本質に迫っていないため、現場の改善に至ってはいないと考えていたところに、この本に出会いました。私は、今の教育現場課題の本質的な解決に繋がるものは「ここだ!」と期待して読みました。
完全版は第8章からなり、大変読み応えがあります。しかし、本書冒頭に述べられている「教師とは、次世代育成の最前線に立つ人間」という言葉が終始一貫しています。
子どもたちにとって身近な大人は教師と保護者。子どもたちは教師の目標達成に向けて生き生きと、そして楽しそうに動いている姿を見て、「いろんな生き方があるんだな」「人生って楽しいものなんだ」「大人になるのも悪くないな」と感じてくれるはず。
まさに教師は、子どもたちが大人になるための人生のモデルであり、希望でもあるという言葉に感動しました。
しかし、今の教育現状はそのようにはなっていません。目の前の仕事に追われ、学校の外に目を向けず、社会と物理的な繋がりを持たない。子どもたちには個性や主体性が求められている一方、教員は個性が発揮できず同一的な指導を求められます。
こんな大人を見て、子どもたちは教員になりたいと思うことはないし、未来に対しても希望が持てません。
著者の方はここで、教師が「セカンドキャリア構築」という視点を持つべきだとしています。第7章では、このセカンドキャリアの持ち方を具体的に紹介しています。私もFacebookに新たな社会的視点でグループを作ろうと頭のどこかで考えていましたが、それを後押ししてくれる具体策が豊富にありました。
本文では、教師と区別して「センセイ」という言葉を使っています。「センセイ」がやるべきことに、「①教師を捨てる②私生活で成功する③学校の外で通用する力を持つ」と述べています。
「センセイ」とは、現在と未来を輝かせる存在。多くの「教師」がこの著書を読み、新たな価値観に目覚め、「センセイ」となって輝けることを強く望みます。
これから長い教員人生を生きる若い教員はもちろんのことですが、あと数年で教員を退職されるベテラン教員にとっても、これから10年、20年の人生を輝かせて生きていくために必読の書です。
千葉県 50代男性 小学校管理職
・読んでみようと思った動機
若い頃から、自分はまさに「従来型の学校教育の枠内で考える」教師でした。それが、当初目指していなかった管理職になる頃から、自分の過去について振り返るようになりました。その際、自分でも意外でしたが、比較的素直に自身の無知さ加減を受け入れることができました。
そして、令和2年春にコロナ禍の中で校長に昇任し、経験のなかった小学校に赴任しました。とにかく書籍を読み漁り、オンラインの研修などに参加し、藁にもすがる思いで学ぶようになりました。その中で、エンパワメントの会員になった共育の杜で配信される著者の書かれていたことに、とても関心をもつようになりました。
・共感できた点とその理由
2章から4章に書かれている「教師の在り方」ついては、まさにその通りだなと思い拝読いたしました。教員という職業についての、きめ細かな分析のされ方に深く感銘を覚えました。
前述のとおり、私自身も著名な校長、元校長の著作やオンラインでの講演から、まだ途上ではありますがたくさんのことを学ばせていただきました。著者の方が書かれているように、多様性を尊重して子どもたちや職員の心理的安全性を保障し、「自律、自走」しながら学び続けるリベラルな学校づくり、そのための土台としてそこに関わる人々のウェルビーイングを学校の最上位目標に置くことなどは、もはや学校経営では必須と考えています。私自身も、実現に向けて取り組んでいるところです。
・特に印象に残った点と、その理由
他の方々と違う感想かも知れませんが、「キャリア」の捉え方について、著者の御主張にとても合点がいきました。
職位柄、日々働き方改革や人材育成について考え、推奨する立場におります。そのため、様々な過去の著作から学ぶのですが、教員の「キャリア」イコール「職位の昇進」と捉えてしまっているものが多かったように思います。私自身その前提にしっくり来ず、モヤモヤした思いをもっていました。
しかし、著者のおっしゃる「キャリア」とは、リタイヤ後も含めた長い人生の中で捉えていらっしゃると感じました。ご自身の教員としての年代ごとの学びに触れておられますが、私自身は2月で56歳になり、より鮮明に60歳以降、70歳以降のことを考えるようになっています。これは、若いときには思いもよらなかったことです。そして、自分の適性の変化についても実感しています。以前は、再任用になれば、一担任、一部活指導者になると思っていましたが、現在はせっかく学んだことを生かして、周囲の方々の育成に参加できたらと思うようになりました。
私は、特に40代後半から50代の職員の皆さんに勧めさせていただきたいと思います。きっと皆さんが抱えていた「キャリア」の捉え方のモヤモヤが晴れていくのではと思っております。
北海道 50代男性 中学校管理職
小学校現場で働く教員です。
著者の考えに共感するところがあり、読みました。
以下のような人に向けて書いてある、と著者は言います。
・教師として自信のない人
・仕事と私生活のバランスがとれていないと感じる人
・学校教育の未来に不安や不満のある人
まさに自分の事だと思いました。
増え続ける仕事。
長時間労働が常態化する職場。
授業準備もままならないまま疲弊していく日々。
心と体の健康が守れず休職する教員の増加。
自分も組織も、変わらないといけない。
変わっていかなければ、子ども達に教員という仕事を勧めることはできない。
そう思っている自分に響く内容が、書かれていたように思います。
響いたところを一部引用します。
・「あなたが教師なら「多様性の受容」から逃れることはできません。というより、むしろ積極的に多様性を尊重する立場にいることを感じていなければならないはずです。」
・「すべての子どもたちの才能を開花させるためにできること。それは、学校が「教えること」を手放し、子どもたちのサポートに徹することです。よって、教師の最終形は「コーディネーター」ではなく、「コンパニオン(仲間)」となります。あるいは「エスコート・ランナー(伴走者)」という位置づけでもいいでしょう。」
今の学校現場の問題点を認識したい、自分自身の未来の方向性を考えたりするきっかけにしたいと考えている方は、一度手にとってみる価値があると思います。
岡山県 30代男性 小学校教諭
この本は、今やブラックと言われている学校現場や教師が、本来の学校や教師の役割ややりがいを再考するヒントになります!
私自身は養護教諭として、支援員として学校現場に関わり、また教師のメンタルヘルスに関する研究をしています。
自身の経験や研究を通してみると、確かに学校や教師が置かれている環境は非常に厳しいと思います。あまりにも厳しい社会からの目や声によって、さらに過酷さは増していると思います。そのことからも国策として学校や教師へのケアが必要だと思います。
しかしながら、それだけでは改善していかない、現場に根付く学校や教師文化があります。そこに気づいている現場教師はたくさんいて、その声をあげている方もたくさんおられます。でもその声はまだ届きにくい現状です。
しんどいけれどやっぱり…学校や教師が自分の置かれている環境や職業と向き合い、そして学校や教師の魅力を自身が感じ、発信していくことが重要だと思います。そのためのウィットが、この本にはたくさん詰め込まれています!
新任の方、ミドルリーダーと呼ばれたくさんの職責に重荷を感じている方、あと退職に向かいやるべきことをしたいけどエネルギー切れも感じている方、教師になりたいけどなんだか怖いなと思っている学生の方、そして学校にかかわるさまざまな関係者の方にも、「学校って?」「教師って?」をしっかり感じられると思います。
私の好きな言葉…「教師脳のアンインストール」です。どういう意味なのか…、ああ分かる分かる!と思った方はぜひ、その意味や方法を習得してください。教師だけではなく、子どもたちの成長を支えていきたいと考える全ての人に読んでいただきたい本です。
40代女性 養護教諭・支援員・大学院生
キャリアのすべてを見通せば「現在地」がわかる
目次を紹介します。
第1章 はじめに
1-1 当協会の目的
1-2 今までのゴールは無効です
1-3 当協会で学べる内容
1-4 当協会の役割
1-5 こんな方を対象にしています
1-6 こんな方には向いていません
1-7 自己紹介
1-8 思い出してみてください
第2章 未来をとらえる
2-1 近づいています
2-1-1.100年人生の始まり
2-1-2.変わり続けるステージ
2-1-3.多様性の受容
2-2 未来の教育
2-2-1.学びたいことを学ぶ時代がやってくる
2-2-2.興味関心は変わり続ける
2-2-3.誰もが「先生」になる
2-3 そして学校も変わる
2-3-1.校則がなくなる
2-3-2.理念のない学校は行き詰まる
2-3-3.生徒は受けたい教育を受ける
2-3-4.学籍移動の自由化
2-3-5.教師はコーディネーターになる
2-3-6.教師は生徒と互恵的関係を結ぶ
2-3-7.公教育には、国策が反映される
2-4 過去を再検討する
2-4-1.形式主義
2-4-2.多様性の不寛容
2-4-3.知識と学歴の偏重
第3章 センセイになるあなたへ
3-1 センセイのメリット
3-1-1.人材育成にかかわることができる
3-1-2.社会的信用がある
3-1-3.終身雇用が保証されている
3-1-4.給料が高い
3-1-5.高い専門性は要求されない
3-1-6.弾力的な時間運用が可能
3-1-7.年休が多い
3-1-8.服装規定が緩やか
3-1-9.上司がいない
3-1-10.常に若々しい気持ちでいられる
3-2 センセイのリスク
3-3 学校という組織
3-4 あなたが育てたい生徒像を教えてください
3-5 年代別センセイの振る舞い方
3-5-1.センセイの20代
3-5-2.センセイの30代
3-5-3.センセイの40代
3-5-4.センセイの50代
3-5-6.60代もセンセイ?
3-6.「キャリア」とは、あなたの人生のすべて
第4章 次世代型教師になろう
4-1.センセイは何からできている?
4-2.「顧客」はだれ?
4-3.今までのセンセイは、成功できない
4-4.NGTの条件
4-5.2つのルール
4-6.センセイがやるべきこと
第5章 仕事で成功しよう
5-1 まずは仕事から
5-2 仕事が人生を決める
5-3 センセイを続けていける、いちばんの理由
5-4 今までのセンセイが落ちるワナ
5-5 NGTなら、こう考える
5-6 原則とビジネス思考で対応する
5-6-1 やることを絞る
5-6-2 時間管理
5-6-3 同僚との関係
5-6-4 生徒との関係
5-6-5 保護者との関係
5-6-6 教科専門性の深化?
5-6-7 部活動指導
5-6-8 分掌業務
5-6-9 自己裁量にフォーカスしよう
5-6-10 人に任せる
5-6-11 得意を伸ばす
5-6-12 キャリアを見直す
5-7 究極のアプローチ
第6章 私生活でも成功しよう
6-1 センセイは、私生活を軽視しがち
6-2 あなたが私生活で成功しなければならない4つの理由
6-3 私生活で成功するための第一歩
6-4 私生活を成功させるための3つの工夫
6-5 センセイが私生活で落ちるワナ
6-6 まず、あなたが成功する
6-6-1 「仕事」を「私生活」に持ち込む
6-6-2 自己研鑽に励む
6-6-3 パートナーと関係を構築する
6-6-4 一人暮らしのあなたへ
6-7 パートナーを成功させる
第7章 セカンドキャリアを構築する
7-1 センセイは退職後を真剣に考えていない
7-1-1.「定年まで勤め上げる」という前提
7-1-2.公務員という地位へのこだわり
7-1-3.変化を嫌う体質
7-1-4.一般社会で通用するスキルを持たない
7-1-5.「自分が歩んできた道」と同じルートに価値を感じる
7-1-6.子どもだけを相手にしていたい
7-1-7.ずっと「ティーチャーズ・ポジション」をとっていたい
7-1-8.忙しくて、そんなこと考えられない
7-2 じゃあ、真剣に考えよう
7-2-1.「定年まで勤めあげる」は、偶然の産物
7-2-2.「価値提供志向」を身につけないと、20年困る
7-2-3.「上から目線」は相手にされない
7-2-4.「教えるだけ」だと、いつか枯渇する
7-2-5.パラレルで考えないと、退職後は燃え尽きて終わり
7-2-6.あなたから「教師」の肩書を取ったら、何が残る?
7-2-7.あなたの生徒は「変化だらけの人生」に漕ぎ出す
7-2-8.教師こそ「多様性」を尊重しなければならない
7-3 たった2つの問いかけ
7-3-1.生徒とあなたと、未来のために
7-3-2.教師の悲しさ
7-4 教師は起業を目指せ
7-4-1.ノープランではセカンドキャリアを構築できない
7-4-2.教師は「自己完結できる仕事」をするべし
7-5 教師が起業に向いている5つの理由
7-5-1.教師は1人1人が「社長」だから
7-5-2.学ぶことに抵抗がないから
7-5-3.社会貢献の意識も強いと思うから
7-5-4.準備に十分な時間を費やせるから
7-5-5.教師としてのキャリア形成がそのまま起業に活かせるから
7-6 リスクを回避せよ
7-7 事例公開
7-7-1.ビジネスの第一歩は「価値提供」
7-7-2.たとえば、こんなやり方があります
7-7-3.ビジネス&自己啓発関連のファシリテーター資格を取得し、セミナーを開催
7-7-4.ブログページを作成・公開
7-7-5.古書店のブックオーナーの1人になる
7-7-6.ポッドキャスト(Anchor)配信開始
7-7-7.stand.fm配信開始
7-7-8.facebookグループ作成
7-7-9.udemyに1stコンテンツ配信
7-7-10.1stオンラインセッション開催
7-7-11.発信プロセスを振り返って
7-8 チャレンジする
7-8-1.誰もが日常的にビジネスに触れている
7-8-2.買ってみる
7-8-3.売ってみる
7-8-4.作ってみる
7-8-5.やってみる
7-8-6.続けてみる
7-8-7.できそうなことから始めてみる
7-9 セカンドキャリア構築に向けた7つのポイント
7-9-1.キャリアの棚卸をする
7-9-2.社会的ニーズを探る
7-9-3.「四方よし」を考える
7-9-4.お金をかける、お金をかけない
7-9-5.発信する
7-9-6.早く始める
7-9-7.誰にも言わない
7-10 セカンドキャリア構築の考え方と必要ツール
7-10-1.PC環境には投資が必要
7-10-2.過去の自分を救ってあげたい
7-10-3.「救ってあげたい過去の自分」は、どこにいる?
7-10-4.「直接スキル」と「間接スキル」
7-10-5.興味関心に忠実になる
7-10-6.自分を知る
7-10-7.現在の関心を突き詰める
7-10-8.未来の展望から考える
7-11 セカンドキャリア構築を加速させる7つの方法
7-11-1.情報を集める
7-11-2.発想を広げる
7-11-3.階層化する
7-11-4.記録する
7-11-5.仲間を集める
7-11-6.環境を整える
7-11-7.時間と空間を確保する
7-11-8.まとめ
7-12 そうならなくても構わない
7-12-1.今を見つめるからこそ、未来を語れる
7-12-2.あなたが最優先すべきは、あなた自身
7-12.3.魅力的であること
7-12-4.大切なのは「学校の外の世界」とつながること
7-12-5.次世代が生きていく世界を知る
7-12-6.セカンドキャリアにつながらなくてもいい
第8章 おわりに
8-1 NGTを目指そう
8-2 人生の本質
8-3 公教育の本質
8-4 メッセージ

未来に何が起こるのか?
教師のリアリティとは何か?
教師に必要な最上位の概念とは何か?
キャリアの本質は何か?
あなたが何歳頃に、どんなライフイベントが起こるのか。
教師に最も必要な視点とは何か?
子どもたちの未来に資する教師の役割とは何か?
この本には、そのすべてが書かれています。
教師には、あらかじめ示された「予定調和」があります。それに身を委ねるか反発するかは、もちろんあなたの自由です。ただ、「何も知らずに日々を過ごすだけでは、人生はあなたの思う通りにはならない」ということだけは、はっきりしています。
あなた次第で、すべてが変わる
もしあなたが関心を持ってくださるのであれば、この書籍の第8章をPDFにして無料で差し上げます。
文字数にして1万1千字。書籍の終章として、「新しい教師像」のすべてのセッセンスが凝縮された内容になっています。
さらに、レビュー(400字程度)を書いていただければ、『完全版』(15万字)のPDFを差し上げます。
下記のアドレスに、
①お名前(フルネーム)
②お住まい(都道府県名のみ)
③お立場(小中高の教師、その他)
をお寄せください。折り返し、ご連絡いたします。
あなたに必要なパートを用意しました
上記『完全版』のボリュームに、少々及び腰のセンセイへ。『分冊版』もご用意しています。
『センセイのキャリアを本気で考えよう!』第1章から第4章まで
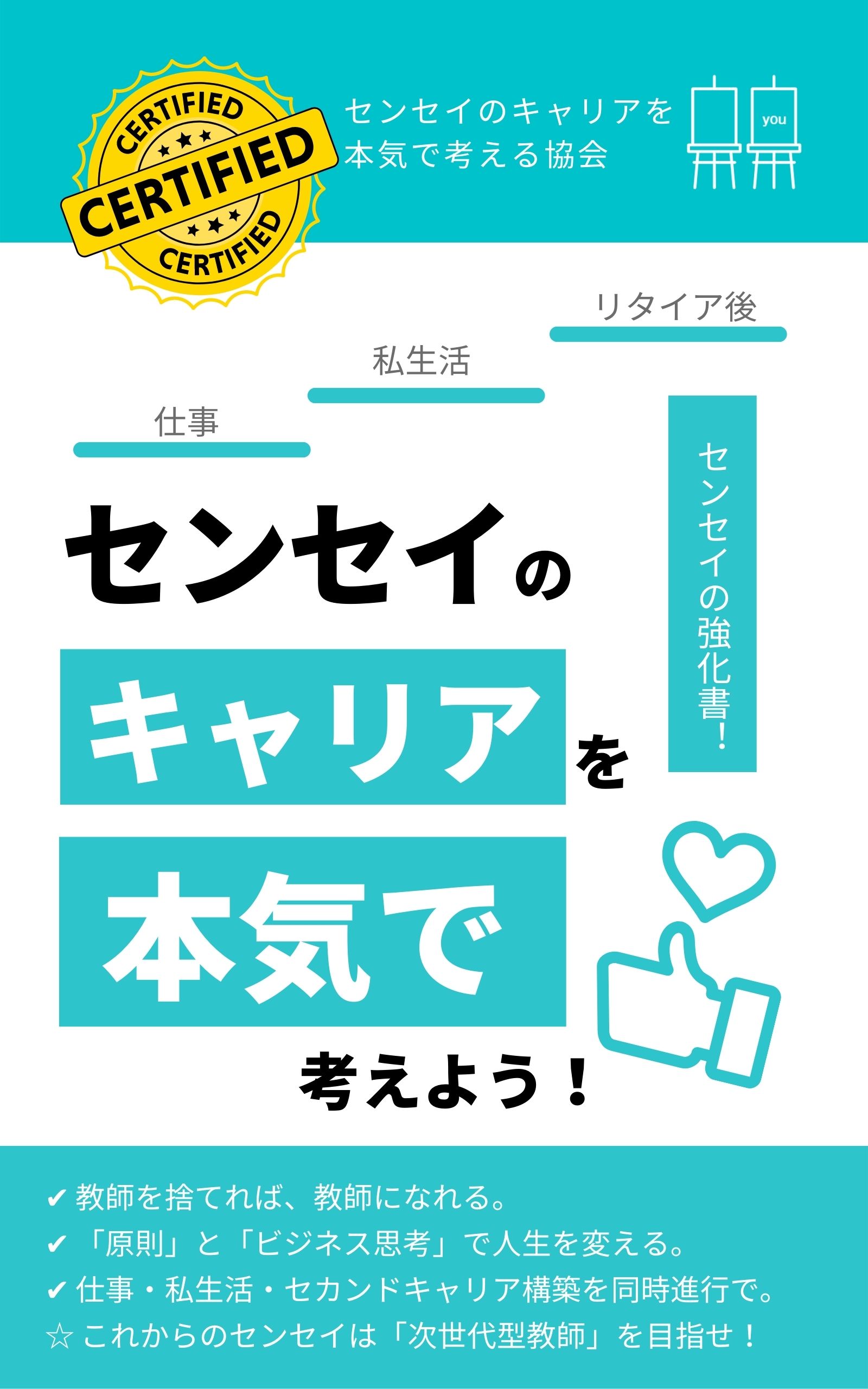
『学校のセンセイが仕事と私生活で成功するために最初に読む本』第5章と第6章
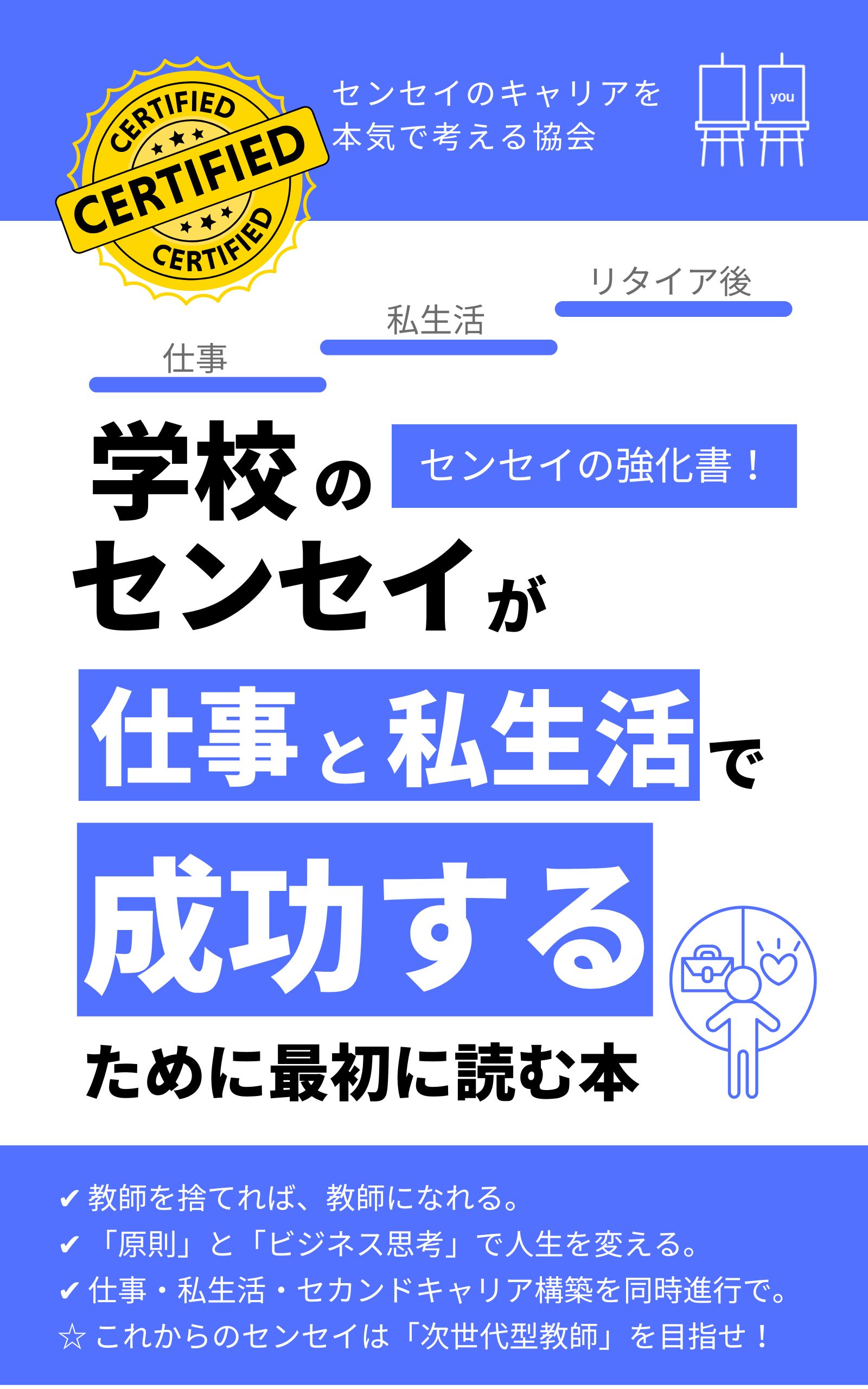
『学校のセンセイがセカンドキャリア構築を考え始めたら読む本』第7章
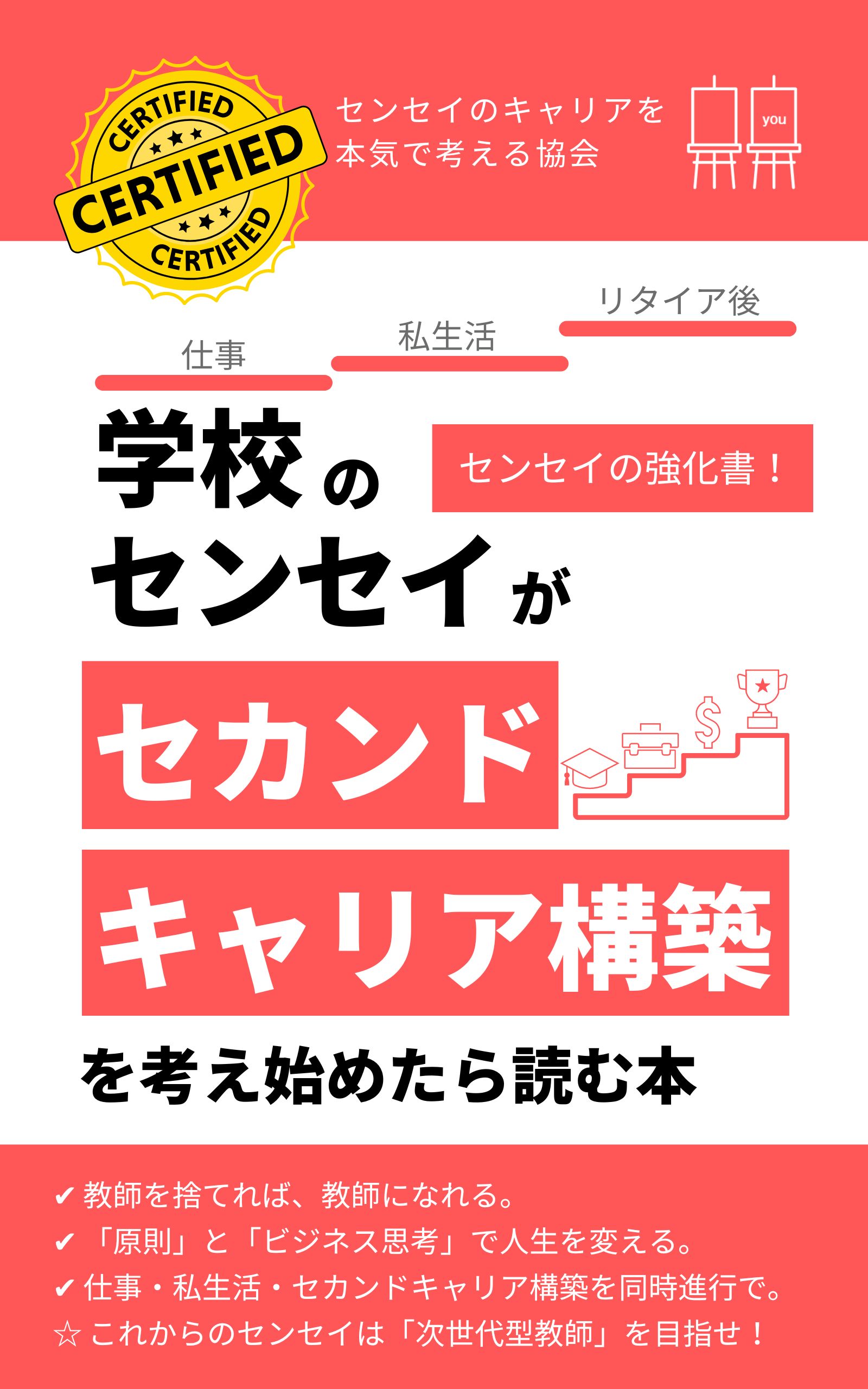
『完全版』のみ、第8章を収録しています。
まず、あなたが「幸せになる」と決める
あなたが最初にやることは、決まっています。
それは、とても簡単なこと。ただ「私は幸せになる」と誓ってください。

もし生徒を幸せにするために、あなたが息を切らしていたとするなら、それは何かが間違っている証拠です。あなたが笑顔でいるからこそ、生徒たちはあなたのまとう雰囲気に感化されて、笑顔になるはずなんですから。
学校のセンセイが変わる時がやってきました。今が、まさに「その時」です。
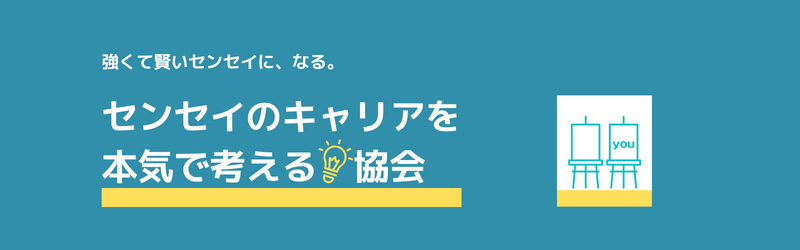
あなたのキャリアが素晴らしいものになるよう、応援しています。

