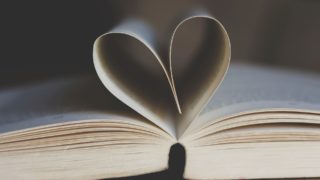「お金」と「時間」、どちらを選ぶ?
あなたは、
「『お金』と『時間』のどちらか一方を好きなだけあげる」
と言われたら、どちらを選びますか?
私なら、「時間」と答えます。
もちろん、私たちに永遠の命は保証されていません。長生きできたとしても、せいぜい100歳程度でしょう。そして「健康寿命」の概念に基づけば、マイナス10歳、つまり90歳くらいまでしか自由が利きません。
さらにそう言われてもなお、疑問が残ります。
「90歳で健康でいられるとは思えない・・・」。
その考えは、正しい。私たちの誰もが、「90歳の時点で健康でいられる」といった夢物語を信じてはいません。どんなに気を遣っても、体の至る所にガタが来ている。それが90歳という年齢です。
私は現在、51歳ですが、自分の体が思い通りに動くのは、せいぜいあと10年くらいだと考えています。30代、40代、50代と大台に乗った時点で、その都度「自由が利かなくなった」と感じてきました。40代の前半くらいまでは運動部顧問として汗を流したり、週1のペースでジムに通ったりしていましたが、ここ5年くらいはほとんど運動をすることはなくなりました。
運動しなくなった最も大きな理由は、「運動機能の衰え」ではありません。加齢による「気力の衰え」です。あれだけ「走りたい、汗を流したい」と強く思っていた気持ちが、加齢とともに急速に減少していく感じが、私自身よくわかります。運動に限らず、いろんなことにチャレンジする気持ちが萎え、何をするにも億劫になってきています。これは私にとって、とても残念なことであり、同時に恐ろしいことでもありました。
「仮に、平均寿命である80歳まで生きたとして、これから先の30年近くを思い通りにならない体とともに、それ以上に萎え切った気力とともに生きていくことは可能なのか?」
ただでさえ加齢は、私たちを保守的にさせます。地位や立場、家族など大切な人の存在、守るべきものが多くなるにつれて、私たちはチャレンジをしなくなる。さらに悪いことに、「黒を白」と言ってはばからなくなります。
私たちは自身の寿命の後半を、かなりの節度や自律心、そして目的意識をもって生きていかなければなりません。
生きている意味
「老いて心身ともに自由が利かなくなるのであれば、やはり若い頃にまとまったお金が必要になってくるのではないか?」
と問われれば、それも違うでしょう。
理由は明白です。確かにお金は人生をある程度豊かにしてくれますが、本当に欲しいものはお金で手に入らないからです。
人によって、欲しいものは千差万別です。そして、現代では欲しいもののほとんどはお金で手に入れられる。しかし、最後には虚しさしか残りません。なぜなら、人間の欲望には際限がないからです。
私たちが最終的に欲するのは、「自分がこの世に生を受けた意味」です。だからこそ、天寿を全うできずに若くしてこの世を去った人たちが懸命に過ごした日々が、あれほど輝きを放っているのです。人生は長短ではありません。人生とは、「生きている間にけどれだけ輝きを放ったか」であり、その輝きを決めるのは常に「あなた自身」なのです。
お金が絶対でないもう一つの理由。それは、「現世でしか使えない」からです。
どんなに金銭的に豊かであっても、棺桶にお金を入れ、あの世に持っていくことはできません。また、係累に残すために蓄財するという考え方もありますが、あなたの死後、例えばあなたの配偶者や子どもたちが幸せになる保証はありません。要は「使い方を知ること」が大切なのであって、それがわからなければ、不幸を引き起こすことも稀ではありません。
以上の理由から、私は「時間」を選びます。50歳を過ぎ、自分だけの自由な時間がかつてに比べて格段に少なくなった今、私にとって時間の価値は高騰しています。おそらく、今後10年以内に訪れるであろうさまざまなライフイベントを考えれば、自由裁量で使える時間は一気に少なくなっていくはずです。その時になって首が回らないようでは、計画性がなかった自分を悔やむことになるでしょう。
今の時代に合った「時間」の増やし方
では、時間を増やすためにはどうしたらいいか。世界的なベストセラーである自己啓発・ビジネス書の『7つの習慣』では、「最優先事項を優先する」という考えに基づいて、「あなたにとって最も価値の高いことでスケジュルール表を真っ先に埋めてしまいなさい」と言っています。
あなたの時間を、「重要度」と「緊急度」の二軸で分類し、「緊急ではないが重要なこと」を最優先事項と位置づけ、その課題に取り組むという考えです。
私はこの考えがとても合理的で真実に近いものと捉えていますが、今回はあえて違う視点で「時間の増やし方」について考えたいと思います。それが、金山慶允という人が言っている、「式神」という考え方です。
金山さんは、
一度やった仕事を、『再利用』できる【コンテンツ】に変えていく。
『残る仕事』をやって、『再利用』していく。
これが未来の時間を増やすポイントだと言っています。
金山さんは、いわゆる情報起業家であり、「式神」とは作成したコンテンツを自分の分身として24時間ネット上に配置する、という意味を持っています。この文脈では「コンテンツビジネス」の有用性を提案しているのですが、私たち一人一人が限りある人生を生きる上で、この考え方はとても重要です。
つまり、
・あなたが教師として取り組んできた仕事は、「再利用」できる。
・あなたのセカンドキャリアを構築するうえで、それまでの蓄積の「再利用」が最も効率的で効果的である。
ということです。
使いまわしの仕事
私は今、「未来につながる仕事」を残そうとしています。それは「使い捨てでない仕事」という意味です。たとえば、このように原稿を書き、ネット上に置き、関心のある人たちに読んでもらうという行為は、私の未来を創る行為だと思っています。
ブログ記事を書けば、他のSNS媒体のように「流れる」ことなく、残り続けます。そして今すぐに読まれなくても、いつか誰かの目に留まった時に、読み手に価値を感じてもらえればいいと思っています。
以前勤務していた高校に、ある先輩教師がいました。
ある時、廊下からその人の授業を垣間見る機会がありました。窓は暗幕で覆い、光を入れない。廊下側の小窓は最小限の明り取りとして覆われることはなく、私はその小窓から中の様子を窺い知ることができました。
その人は、パワーポイントを使って授業をしていました。生徒にはプリントを配布し、講義と書き込みで授業は構成されていました。
私の当初の印象はこうでした。
「手抜きだな。」
「授業とは、大きなエネルギーを使って生徒に向きあうことだ」と考えていた当時の私にとって、スライドを流しながら淡々と進める授業は、決して高い価値を感じるものではなかったのです。
私は休み時間にその人のところへ行き、パワーポイントを使った授業をしようと思った意図について聞いてみました。すると、
「生物は教える内容がそんなに変わることがないから、スライドを作った方が使いまわせると思ったんだよね。」
その時の私は、不遜にも「同じことの繰り返しなんて、授業じゃない。もっと生徒の反応をダイナミックに引き出せるような他のやり方があるはずだ」と感じていました。
しかし、今となってみれば、その人がいかに効率のいい進め方をしていたのかがわかります。授業内容について、基本的な核となる部分については、あるいは何年経ってもその重要性が変わらない点については、パワーポイントのようなデジタルコンテンツは非常に有効であるということです。
・板書する時間と労力を省略できる。
・講義や生徒の見取りに専念できる。
・聴覚だけでなく視覚に訴えることができる。
・生徒の注意力を維持できる。
そして、
・何年も使える。
これです。最初にあれだけのスライドを作りこむのには、大きな労力が必要だったでしょう。しかし、一度作ってしまえば、自身がその科目を教え続ける限り、そして教師を続ける限り、永遠に使い続けられます。結果として時間がつくられる。その浮いた時間は、次のアイディア探索に使えます。
仕組みが時間を生み、その時間が新たなアイディアを生む。これは間違いなく、「正しい」連鎖と言えます。私は自身の不明を恥じるばかりでした。
「完璧なノート」の虚しさ
ところで、これはその人が「生物」のような、ほとんど内容的に変化のない科目を教えていたから実現できたことなのでしょうか。私はそうは思いません。
確かに「理科」という教科指導において、デジタルコンテンツを作ることは比較的容易であるとは思います。それは普遍的な原則を内容的に扱っているためです。
ところで、たとえば私が教える教科は「国語」です。それはさらに「現代文」「古文」「漢文」「国語表現」などの領域に分かれます。
「国語」、特に「現代文」領域は、内容の変化は大きいものです。教科書が数年単位で変わり、それに応じて教える単元(教材)が変わります。さらに異動があれば、異動先に応じて教科書も変わる。生徒に応じて単元も変わります。
加えて、「国語」という教科は生き方や人生観と直結する点が非常に多いため、「教え方が変わる」ことがどんどん出てきます。同じ教材であっても、25歳の頃の私と50歳の私では、受け取り方や着眼点が大幅に変わってくる。結果、毎年教材研究をやらざるを得ないという状況が生まれます。
教師になりたての頃は、私もノートを作っていました。現古漢別々に何冊も、それこそ4色も蛍光ペンを使って、「綺麗な」ノートを作って悦に入っていました。「これだけ詳細に網羅しておけば、退職するまで使えるはず」といった、根拠のない確信をもって(笑)。
しかし、現実は全く違っていました。2年目、3年目くらいまでは、王道的な作品の教材研究にはそのノートを参照していました。それが4年目以降、できなくなりました。もともと「詳細で網羅的」な知識をまとめていただけだったので、ノートを見返しても、何の驚きも発見もないことに気づかされたのです。
「知識の披歴は何の役にも立たない」と感じていたその当時の私にとって、蓄積してきたノートは「過去の栄光」に過ぎませんでした。私はノートを捨てました。
汎化の可能性を考える
「国語」でも、使いまわせるコンテンツは作れると思います。
たとえば、
・各作品のメインテーマの候補をまとめておくこと。
・当該作品を通じて身につける考え方や視点の候補をまとめておくこと。
・当該作品を分析するためのツールの候補をまとめておくこと。たとえば「思考のフレームワーク」のような汎用性の高い思考プロセスの候補を用意し、どんなフレームワークで分析すると楽しく、比較的明確な結論にたどり着けるかを意識すること。
などが挙げられます。
以前の私であれば、現代文なら「難解箇所の読解と説明の仕方」、古典なら「語釈と文法事項と文学的背景」あたりを網羅することばかり考えていたはずです。
しかし、そんなことは今の私にとっては些末なことです。わからなければその都度意味を確認し、生徒と一緒に改めて考えるようにしています。一度覚えた「完璧な」解釈を、物知り顔で生徒に伝えることの無意味さは、十分わかったつもりです。
どんな教科でも、「使いまわせる」コンテンツは作れる。その教材のポイントを押さえれば、浮いた時間で新たなアイディアを生み出し、生徒に提供することが可能になります。
「コンテンツ」の本質的価値と活かし方
そして、私たち教師が本当に生み出さなければならないコンテンツは、さらに遠い未来につながるものです。前出の金山さんは、こう言います。
・今の時間の使い方を変える
・他人の役に立つ「コンテンツ」を作る
・全体の設計を考えて『リンク』を作る
このように考える視点は、「情報起業」に基づいています。しかし、その考え方の汎用性は高い。
これは、「人生の捉え直し」です。時間が有限であること、生きた証は時間の長さに比例しないこと、生きた価値はその人自身の納得感に左右されること、これらは自明です。私たちは少なくとも、これらのことを意識して日々を送る必要があります。
加えて、金山さんはこう言うのです。
・あなたの時間の蓄積を、価値あるものとして残しましょう。
・その価値は、あなただけでなく他の誰かにとって役に立つものにしましょう。
・複数の領域で「価値あるもの」を残し、関連づけることによって価値を増幅させましょう。
長年教師を続けていながら、このような視点に立ったことはありませんでした。
「私の生きた時間、重ねてきた経験そのものが価値になる。」
「私は価値提供という視点で教師の仕事に取り組んでこなかった。」
「わずかな優位性でも、かけ合わせれば価値を高めたり希少性を生んだりすることができる。」
私の中で、パラダイム転換が起こった瞬間です。
こんな言葉があります。
「労働の対価は、価値提供の大きさとその範囲に応じる」
つまり、「より多くの人に、より大きな価値を感じてもらうことが大切だ」ということです。あなたの作ったコンテンツが、多くの人にとって有意義な、役に立つものであれば、あなたの人生そのものが大きな意味を持ち始めることになるでしょう。さらには人生の終わりの瞬間に、一つも思い残すことなくこの世を去ることができるのではないでしょうか。
そのためにも、あなた独自の「コンテンツ」を作り続け、近い将来に多くの人の目に触れさせることを考えてみてください。そして浮いた時間を使って、新たなアイディアを吸収し続けていってください。きっと効果的で充実した人生を送れるはずです。
公立高校の現役教師。教員経験28年(2021年3月末現在)。「教師は、仕事&私生活&リタイア後の人生、すべてにおいて成功すべし!」が信条。教師が成功すれば、学校は変わり、生徒も魅力的な大人に成長します。まず教師であるあなたの成功を最優先課題にしましょう。
☑心理学修士(学校心理学)
☑NPO法人「共育の杜」オンラインサロン『エンパワメント』専任講師
☑一般社団法人7つの習慣アカデミー協会主催「7つの習慣®実践会ファシリテーター養成講座」修了。ファシリテーターを3年務め、セミナーを開催。
☑ハンドルネーム「角松利己」は角松敏生から。
「原則」&「ビジネス思考」で、教師が自由になるための方法をお伝えします。