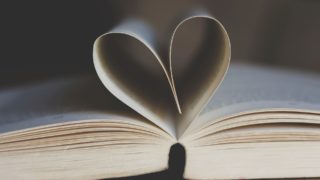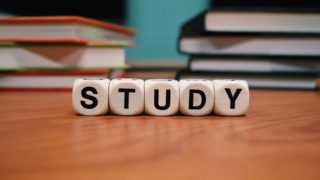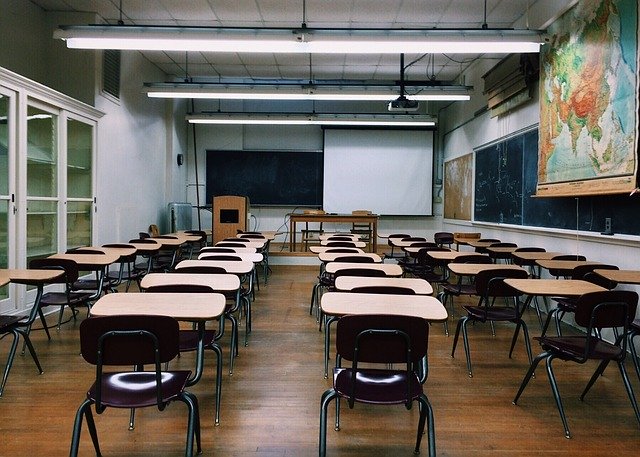皆さんこんばんは角松利己です!
新型コロナウィルス感染症対策で、多くの人が行動制限を受けています。
今まで、当たり前のように過ごしていた日常が奪われているわけですが、「こういった非日常時に何ができるのか?」について考えてみたいと思います。
与えられた環境でどうするか?
安倍首相による2020年3月2日の「臨時休校要請」以降、子どもたちは登校していません。
今日は2020年3月13日。私のいる都道府県では公立高校の合格発表日に当たります。高校入試はかなりの日数を割く必要があるため、この時期に生徒たちの姿を見ないことに違和感はありません。ただ一方で、4月以降に登校可能になるかどうか、見通しは立っていません。
明確な方針が示されない中、私たちが考えなければならないことは一つです。それは、
「与えられた環境で何ができるのか?」
ということです。
世間では、「リモートワーク」がはやっていますよね。
ここでの問題意識は、「通勤せずに仕事ができないか?」という点です。
「通勤のコスト」については、きっと多くの人が「なんとかできればなぁ」と普段から感じていた点ではないでしょうか? 圧倒的なコストは「膨大な時間が通勤によって消費されること」です。ちなみに、「消費」は「代価に見合ったものを受け取ること」なので、通勤時間を使って娯楽を追求するのは「浪費」に、同じ時間で自己成長のために学ぶ行為は「投資」になります。
私は自動車通勤をしていますが、理由は「帰りたい」と思ったときに、すぐに帰れるからです。公共交通機関を使って通勤することも可能ですが、私にとってはダイヤに縛られるデメリットが余りにも大きいので、選択しません。ですから、私にとっての通勤時間は、「ダイヤに縛られない」環境を手に入れるためのものになるので、「消費」レベルでしょうか。
リモートスタディは、どの程度可能なのか?
さて、「通勤せずに仕事ができないか?」という問題意識に対しての一つの回答が、「リモートワーク」なんですが、現時点で教師が考えるべきは、「生徒に対してリモートスタディがどの程度可能なのか?」という点です。
新型コロナウィルスの影響が長引けば、必然的に、「リモートスタディ」について考えざるを得ませんよね。確かにいくつかの学校では、子どもたちにタブレットを持たせて遠隔操作で健康状態や自宅での過ごし方を把握し、さらに授業を行っています。
ただし、このような環境が実現するのは、ある程度の資金が確保されていたり学校自体の質に拠ったりしているため、そういった環境にない学校にとってのハードルは高いと考えられます。
現実的な方法としては、「各科目の記入式課題をメール添付で配信し、自宅で取り組んだ結果を返信する」という形が考えられます。先進校では「1週間に1回程度の頻度で各科目の授業動画を撮り、生徒に配信する」などの取り組みを行うことも可能でしょう。
しかし、やはり多くの学校において、それを実行することは難しい。あとは、たとえばクラス単位で生徒を時間差登校させて、少人数限定という条件の中で数時間の授業を実施し、課題をどっさりと渡して次回提出ね、という形が現実的でしょう。この手法も、いくつかの学校がすでに実行しています。
学校が「無力だな」と思う時は、こういう時です。
「生徒が登校できない状況におかれる」
こんなことは、普段の感覚では考えられない話です。しかし、そのようなケースが日々、起きているのも事実。だから、私たちは「そのようなケース」について、普段から考え続ける習慣を身につけなければなりません。
想定できないことを想定するには、「未来」への視点が必要
自己啓発およびビジネス関連書籍として世界的な名著である『7つの習慣』には、「第3の習慣」として、「最優先事項を優先する。」という考え方が述べられています。
要点はただ一つ。
「緊急ではないが、重要なことに取り組む。」
これだけです。
「最優先事項を優先する」とは、「今すぐに必要ではないけれど、長期的視点で見た場合、ほぼ間違いなく直面するライフイベントに対して、あるいはあなたの願望を実現する上必要な事柄に対しては、普段からよく考えたり、準備しておいたりすることが大切ですよ」ということを意味します。
私は、「この最優先事項を優先する行為は、仕事に限らず人生の70%を占める」と思っています。「未来というゴール」を明確にイメージしながら、「現在」に取り組む。そうすることで、「現在」がどんどん良くなっていく。「現在」と「未来」にパラレルで取り組むことが相乗効果を発揮して、大きな効果を生み出すということです。
生徒が登校できない状況におかれている今、できることについてはじめて考えるのは「時すでに遅し」ですが、これから起こり得るさまざまな可能性について検討を始めるのは、今すぐにでもできることです。たとえば「生徒のリモートスタディを実現するためのインフラ整備」は、形式にこだわらなければすぐにでも実現可能です。
新種の感染症発生をイメージしながら仕事をしている学校は、ないと思います。一方で、過度なリスク管理は、ほとんど意味がありません。
ただ、これだけは言えます。
新たな「何か」が、仕事や人生を捉え直す契機になる。
大切なのは、「新たな何か」は間違いなくいつかはあなたのもとに訪れるということ。
そして、あなたはその「何か」に対応する必要がある、ということです。
もしあなたが「新たな事態」に正しく対応したいと望むなら、次のことについて考えてみて下さい。
非日常を乗り切るには、日常におけるあなたの思考がすべてということ。
そして、あなたに与えられている環境が非日常を乗り切る上であまりにも小さかったり、あるいは合理的ではなかったり、あるいは長期的な視点を欠いていたりするものであるならば、
あなたの「環境」を拡大する。
このことについて、いつも考えておいて下さい。
自らの環境を拡大していく。
リモートワークの加速、ネット経由でのやり取りの活発化、「対面しなくてもできること」と「対面が必要なこと」の見極めと割り切り。社会はこの方向に移行しています。
学校は、どうか?
「新たな何か」に遭遇している今、全国に80万人いる多くの「あなた」に考えて欲しいことです。
公立高校の現役教師。教員経験28年(2021年3月末現在)。「教師は、仕事&私生活&リタイア後の人生、すべてにおいて成功すべし!」が信条。教師が成功すれば、学校は変わり、生徒も魅力的な大人に成長します。まず教師であるあなたの成功を最優先課題にしましょう。
☑心理学修士(学校心理学)
☑NPO法人「共育の杜」オンラインサロン『エンパワメント』専任講師
☑一般社団法人7つの習慣アカデミー協会主催「7つの習慣®実践会ファシリテーター養成講座」修了。ファシリテーターを3年務め、セミナーを開催。
☑ハンドルネーム「角松利己」は角松敏生から。
「原則」&「ビジネス思考」で、教師が自由になるための方法をお伝えします。