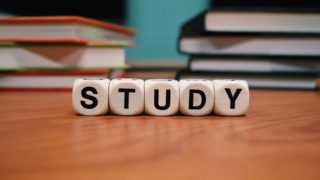第5の切り口
佐藤正遠さんは自身のメルマガで、
かつて仕事は、「業種、業態、役職、年収」という4つの切り口で分類されており、この4つが分かるとその人がどんな人なのかが、それなりの精度で理解できたが、現在は「労働にレバレッジが掛かっているかどうか?」という切り口が加わった。
と言っています。
ここでは、「第5の切り口」が示されています。それが「労働にレバレッジをかける」という考え方です。「レバレッジ」は、「てこ」を指しています。「小さな力で大きな動力を生む原理」のことですね。
昭和の時代には、たとえば「営業職」は、「レバレッジを掛けずに働いている人」が多かったそうです。彼らは、次のような働き方をしていました。
この人たちは毎月、月初にメーターがゼロに戻って、そこから競争が始まるんですね。先月100件売ったといっても、月が変わったら全員がゼロに戻ってしまうわけです。それを延々と毎月繰り返していたわけです。
これでは厳しいですよね。やってきたことが自身のキャリアとして積み重なっていかないのであれば、「仕事を頑張ろう!」と考える人はおそらくいないのではないでしょうか?
佐藤さんは続けます。
自分が今やっている頑張りが、今だけにしか効いていないのなら、レバレッジは掛かっていないんです。そういう働き方をしていると、毎月毎月メーターがゼロに戻ってしまうんです。だからいつまで経っても一向に楽にならないんですね。
そうではなく、今やっていることが、未来に繋がる、未来の自分を助けてくれるという設計図を描くべきなんです。
さて、ここまで読んだあなたは、どう思っていますか?
「今まで取り組んできた仕事は、その時々の頑張りだけで終わっていたんじゃないか・・・?」
「教師になって何年にもなるけれど、きちんと未来への設計図を描いてこないまま仕事をしてきたんじゃないか・・・?」
こんなふうに思ったとしたら、大切なことに気づいてしまった今、あなたはシフトチェンジしなければなりません。
学校の仕事は「メーターがゼロに戻る」仕事
ところで、学校の仕事、いわゆる「校務」に対するあなたの取り組みの現状はどうでしょうか。
校務は、授業、部活動指導、校務分掌業務、保護者対応、クラス経営、生徒指導、進路指導と、多岐にわたります。では、これらのうち、「未来への蓄積」が想像できる領域はどこか?と問われたら、あなたはどう答えますか?「そんなのすべてに決まっている!」と断言できるでしょうか。
確かに、どの領域も、教師であり続ける限り「蓄積」可能であるように思えますよね。教壇に立てばたつほど授業はうまくなるという側面はありますし、部活動指導のスキルも、同じ競技種目を担当し続ければ造詣は深くなるでしょう。同様に、残る他の領域ほとんどすべてにわたり、「やればやるほどうまくなる」ということが言えるような気がします。
しかし、現実はそうではありません。
公立学校の職員には「異動」がついて回ります。そして異動先ではどの領域においても、ほぼ間違いなく「最初からのスタート」を余儀なくされます。
たとえば野球部顧問の長い人が異動先で再び野球部顧問に就けたとしても、部員数や志向性によって目標は変わってきます。さらに言えば、同一部活動を転々とできるのはまだいい方で、異動先にあなた以上の専門家がいれば、他の部活動顧問に回されます。どの領域でも、基本は一緒です。
「教師とは、そういう仕事だ。」と言ってしまえばそれまでですが、これでは教師が自身の「ウリ」を見出すことは永久に不可能です。ウリが見つからないまま多くの部活動や分掌を転々とし、その時々の要求に応え、トラブルに対処しながら、定年を迎えることになるのです。自身の専門性も深まらないまま、毎年ゼロベースで仕事に取り組む。これはキツい話です。
加えて、一般的に学校は保守性が高く、異動しても勤務校の雰囲気に慣れるまでは様子を伺い、その学校に慣れたころには次の勤務校へ異動、という流れになっています。誤解を恐れずに言えば、
「いかに異動先の雰囲気に慣れ親しみ、同僚や生徒と仲良くし、トラブルを起こさずに次に進んでいく」というゲームを余儀なくされるのが、「教師」という職業です。
仮に意識の高い教師が勤務先で「結果」を残したとしても、それが「システム」として残り続ける可能性は、極めて低いと言えます。
学校は、利益を生まない組織です。ならば、良いシステムを残す必要はありません。その時々にその学校を構成する教師が、「その時に頭の中にあること」を言い合ったうえで、特定の意見に押し切られるか、妥協すればいいだけの話です。
つまんないですね(苦笑)。
学校でレバレッジを利かせる方法
では、「メーターをゼロに戻さない仕事をする」ためには、どうしたらいいのでしょうか?
つまり、あなたのやってきた仕事が「蓄積」され、何度異動しても、どこへ異動しても、その場その場で輝きを放ち、あなたがこの仕事を辞めた後もセカンドキャリアを築いていくための資産になるとしたら、どうでしょうか。最高だとは思いませんか?
もしあなたがそれを望むなら、「レバレッジをかける」ことです。
「てこの原理」を使って、あなたがほんのわずかな力で大きな成果が出せる領域を発見し、その領域の専門家になり、その領域だけに専念することです。そうすることで、あなたはどこにいても居場所を確保し、周囲から求められ、自信をもって仕事に臨めることでしょう。
そして、それを実現するためには「キャリア視点」が不可欠になります。
あなたが教師として何歳ころまでに何を実現しておきたいのか、これについてプランを立てる必要があります。
あなたが校務分掌として教務部に関心があり、適性も低くないと判断したならば、教務部であり続けることです。仮に異動初年度で希望が叶わなかったとしても、常に学校業務について思いを巡らせ、メモを取り、改善プランを頭の中で練っておく必要があります。そうすれば、次の分掌で必ず生きてきます。
理由は簡単で、「あなたがそのことをずっと考えていたから」です。
このことはプライベートについても言えることです。何歳までに結婚し、子どもを持ち、家を建てるのか。子どもをどの学区に通わせたいのか。実家の問題を片付けるのはいつか。年老いた親との接し方をどうするのか。およその見当はつくと思います。
そして、セカンドキャリアをどうするのか、です。
セカンドキャリアの構築は、あなたが教師生活をどのように送ってきたのかということが、おそらくすべてになります。数十年にわたる教師生活における蓄積が、あなたのセカンドキャリアの方向性を決めます。
もちろん、蓄積の結果に縛られる必要性はないのであって、それまでとはまったく方向性の異なるセカンドキャリアを志向する可能性だってあるでしょう。
しかし、基本的に人間というのは、一本の糸でつながっているものです。あなたが長年考えてきたことが、取り組んできたことが、あなたの好きなことであり、あなたが得意な、つまりレバレッジを利かせることのできる、少ない力で大きな効果をあげることのできる領域なのです。
成功のカギは本質と効果性の追求
私の場合は、汎用性の高い本質の追求というのがライフワークになっています。教科指導でも、部活動指導でも、分掌業務でもありません。ちなみに、それらはみな、50歳を超えた今もなお私のキャリアを構成する要素にはなっていません(笑)。どの領域もそこそここなしますが、得意分野と言えるものではありません。
現在の私のベースになっているものは、「原則」と「ビジネス思考」です。
普遍性・汎用性の高い原則は、勤務先を問わず、生徒を問わず、私に落ち着きとやる気をもたらしてくれます。そして合理性と効果性を追求するビジネス思考は、私の仕事や家庭生活をシンプルにしてくれると同時に、大切なことに思いを巡らす時間と余裕を与えてくれます。どちらも、私にとっては不可欠なものですし、おそらく私だけでなく、多くの人たちにとって大切にしてほしい考え方であるはずです。
ですから、私は職場では仕事らしい仕事はしていません。厳密にいえば、校務全般に時間やエネルギーなどのコストをかけないようにしています。私がコストをかけていることは、次のような点です。
「どうしたら仕事が早く終わるのか?」
「どうしたら質の高い仕事ができるのか?」
「どうしたら多くの人の仕事がラクになるのか?」
「最も汎用性の高い考え方は何か?」
「どうしたら信頼関係を構築できるのか?」
このことだけを考えた結果、ほぼ定時に帰れるようになりました。プライベートでもできるだけ家族との時間が取れるようになり、セカンドキャリア構築を見据えながら外の世界に目を向け、将来につながる種を蒔いています。
あなたは限りある自己資源をどこに投入していますか?
もし、あなたがあなたに与えられた人生を生き切りたいと願うのであれば、次のことを考えてみてください。
◎多岐にわたる仕事のうち、レバレッジをかける領域を見つけること。
その領域は異動するたびに変えるのではなく、ずっと考え続けること。
◎あなたのキャリアを見通すこと。仕事、プライベート、退職後のすべてのキャリアをパラレルに見通すこと。
◎(これは私のやり方ですが)汎用性と効果性を追求すること。
どんな場所でも使える考え方や、少ない労力で大きな効果を得られる方法を常に考え続け、実行すること。
この3つにチャレンジすることで、
あなたは「最強の教師」に、いえ、「最強の人生」を送ることができるでしょう。
公立高校の現役教師。教員経験28年(2021年3月末現在)。「教師は、仕事&私生活&リタイア後の人生、すべてにおいて成功すべし!」が信条。教師が成功すれば、学校は変わり、生徒も魅力的な大人に成長します。まず教師であるあなたの成功を最優先課題にしましょう。
☑心理学修士(学校心理学)
☑NPO法人「共育の杜」オンラインサロン『エンパワメント』専任講師
☑一般社団法人7つの習慣アカデミー協会主催「7つの習慣®実践会ファシリテーター養成講座」修了。ファシリテーターを3年務め、セミナーを開催。
☑ハンドルネーム「角松利己」は角松敏生から。
「原則」&「ビジネス思考」で、教師が自由になるための方法をお伝えします。